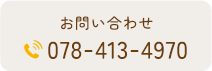増加傾向!?小児気管支喘息(ぜんそく)とは
 小児気管支喘息は、気管支の炎症により呼吸困難を繰り返す病気です。
小児気管支喘息は、気管支の炎症により呼吸困難を繰り返す病気です。
わずかな刺激でも気管支が腫れ、痰が分泌され、発作が起こります。
慢性的な炎症を抑える適切な治療の継続が重要です。
炎症が長引くと気管支が硬くなり、治療が困難になることもあります。
自然治癒することもありますが、早期の治療開始が大切です。
小児喘息は増加傾向にあり、現在の患者数は全体の約6%です。
住宅の高気密化によるダニやホコリの増加が原因の一つと考えられています。
発症は2~3歳頃が多く、小学校入学までにほとんどの子どもが何らかの症状を経験します。
乳幼児期に発症した子どもの約6割は小学校入学までに症状がなくなりますが、その後も発作が続く場合は成人まで症状が持ち越される可能性があります。
喘息は治療が難しい病気ですが、近年、新薬の開発により、多くの患者さんが日常生活やスポーツを楽しめるようになりました。
小児気管支喘息の症状
喘息発作では、気管支が狭くなり、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴とともに呼吸困難を繰り返します。
風邪でもないのに咳が続くこともあります。
症状は夜間や明け方に悪化しやすい傾向があるため、お子さんの状態に注意深く観察することが大切です。
病院を受診する目安
- 吸入薬で症状が治まっても、翌朝には受診する。
- 吸入薬使用後3時間以内に再び呼吸困難になる。
- 唇や顔色が悪い、意識がもうろうとするなどの症状が現れる場合は、すぐに救急車を呼ぶ。
発作が起きた時の対処法
- 医師から処方された薬を使用する。
- 新鮮な空気を吸わせる。
小児気管支喘息の発症理由と、症状が悪化する原因は?
 小児喘息の多くは、ダニやハウスダスト、花粉などのアレルギーが原因となります。
小児喘息の多くは、ダニやハウスダスト、花粉などのアレルギーが原因となります。
これらのアレルゲンは喘息を悪化させる要因となります。
その他にも、感染症、気圧の変化、冷たい空気、煙、ストレスなども喘息を悪化させる可能性があります。
発作を予防するためには、悪化要因を把握し、適切な対策を講じることが重要です。
当院では、喘息の悪化要因に関する情報提供や生活指導も行っております。
アレルゲン
ダニ、カビ、ペットの毛やフケ、虫の死骸や糞、繊維、花粉などは、吸い込むことでアレルギー反応を引き起こすアレルゲンです。
こまめな掃除でアレルゲンを減らし、清潔な環境を維持することが重要です。
血液検査などによるアレルゲン検査を実施しています。
感染症
上気道などにウイルス性の炎症を起こす風邪は、喘息発作のきっかけとなることもあります。
当院へ早めに受診し、悪化させずに速やかに治癒に努めましょう。
風邪を予防することも大切です。
大気汚染物質
気管支喘息では、慢性的な気管支粘膜の炎症により過敏な状態になっています。
大気汚染物質などの刺激によって喘息発作が引き起こされることがあります。
原因となる可能性のある物質は、タバコの煙、花粉、PM2.5、花火やお香の煙など様々です。
特に、タバコの煙は喘息患者にとって有害です。
ご家族に喘息の方がいらっしゃる場合は、家庭内での喫煙は避け、屋外で喫煙した場合でも、しばらくは室内に入らないように配慮が必要です。
呼気にも原因物質が含まれている可能性があるためです。
天候
気圧の変化、気温の変化、乾燥は、喘息発作の誘因となることがあります。
例えば、台風などによる急激な気圧の変化、冬場の屋外への外出、低温で乾燥した環境、昼夜の大きな気温差などが挙げられます。
運動
運動誘発喘息は、運動時の呼吸の変化により口呼吸となり、冷たい空気が気道に入り込むことで発作が引き起こされる症状です。
長時間のランニングなど、軽い運動では発作が起きなくても、激しい運動で発作が起こることもあります。
特に冬は空気が冷たく乾燥しているため、発作が起こりやすい傾向にあります。
運動誘発喘息の経験があっても、適切な治療を継続することで運動の制限は徐々に解除され、活動の幅を広げることが可能です。
状態に合わせてある程度の制限は必要ですが、諦める必要はありません。
ストレスや睡眠不足などの生活習慣
強いストレス、寝不足、疲労は、喘息発作を誘発しやすいため注意が必要です。
小児ぜんそくの検査
特異的IgE抗体検査
(イムノキャップラピッドアレルゲン8)
小児喘息では、ダニなどの吸入抗原に対するアレルギー検査が重要です。
当院では、お子さんの負担を最小限に抑え、迅速に結果を得られる「イムノキャップラピッドアレルゲン」を推奨しています。
この検査は指先から少量の採血(0.1ml)で行い、約20分で結果が判明します。
特に3歳以下のお子さんのように、血管確保が難しい場合でも検査可能です。
検査項目は、「スギ」「ダニ」「イヌ」「ネコ」「カモガヤ」「ブタクサ」「ヨモギ」「シラカンバ」の8項目です。
一方、従来のIgE抗体検査は5~10mlの採血が必要で、外部機関に検体を送付するため、結果が出るまでに時間を要します。
「イムノキャップラピッドアレルゲン」は、検査項目は限られますが、スギやダニなど、主なアレルゲンを迅速に確認するのに有効です。
呼吸機能検査
(スパイロメトリー)
肺機能検査は、呼吸を通じて肺の機能を評価する検査です。
この検査で得られる重要な指標は、「1秒率」です。
1秒率は、個人の肺の大きさ(努力性肺活量)に対して、1秒間に吐き出せる息の量(1秒量)の割合を示し、気管支の狭窄の程度を反映します。
小児喘息の場合、1秒率が80%未満であれば、気管支が狭くなっている「閉塞性障害」と診断されます。
また、フローボリューム曲線も重要な指標で、喘息では特徴的な下に凸の形状を示します。
喘息と診断されている方では、治療前後の1秒量の変化を比較することで、気管支の拡張状態を確認できます。
努力性肺活量は肺の大きさを示します。
呼気一酸化窒素濃度測定
(NO検査)
呼気NO(FeNO)検査は、気道の炎症状態を評価する検査で、喘息や咳喘息の診断、そして治療効果の判定にも役立ちます。
検査方法は、10秒間一定の速度で息を吐き出すだけです。
好酸球性小児喘息の場合、喘鳴がありFeNO値が35ppbを超えていると診断の目安となります。
FeNO値は治療によって改善するため、治療効果の指標としても有用です。
ただし、FeNO値が低い喘息も存在するため、結果の解釈には注意が必要です。
ピークフローメーター
ピークフローメーターは、ご自宅で手軽に肺機能を測定できる機器です。
「瞬間最大風速」を測定することで、肺機能検査の「1秒量」と同様に気管支の狭窄度を評価できます。
この機器は、患者さんご自身で病状を客観的に把握するのに役立ちます。
ピークフローメーターの利点は、場所や時間を選ばず、いつでも簡単に測定できることです。
これにより、治療効果の経時的変化、呼吸困難との関連、1日の気道狭窄の変化(日内変動)などを確認できます。
日内変動は気道過敏性を示す指標であり、病院で行う肺機能検査では評価できないため、ピークフローメーターは大変有用です。
また、治療への反応性を経時的に確認できる唯一の機器でもあります。
いつでもどこでも測定できる手軽さも大きなメリットです。
小児気管支ぜんそくの治療法
発作時

- 換気をする
- 薬を服用する、吸入する
- 楽な姿勢をとる
喘息発作時の対処法を理解しておくことは重要です。
医師から処方された気管支拡張薬があれば使用してください。
発作時は、仰向けよりも体を起こした方が呼吸が楽になります。
小さなお子さんの場合は、抱っこしてあげると安心し、体を冷やすことも防げます。
これらの対処法でも改善が見られない場合、特に呼吸が非常に苦しい、夜間に眠れない、何度も嘔吐するなどの症状が続く場合は、速やかに当院か救急病院を受診してください。
ぜんそくの長期管理
喘息の大きな特徴は、気道の慢性的な炎症です。
炎症により傷ついた気道粘膜の修復には時間を要します。
傷ついた部分は刺激に敏感になり、些細なことで発作を起こしやすくなります。
この状態が続くと、肺機能の低下につながる可能性があります。
喘息の長期管理の目的は、発作をコントロールし、健常なお子さんと変わらない日常生活を送れるようにすることです。
ぜんそく治療の
「基本的な三要素」
環境整備
喘息発作の誘因となるものを生活環境から取り除きましょう。
運動療法
基礎体力の向上に努めましょう。
薬物療法
患者さんそれぞれのライフスタイルと重症度を考慮し、最適な治療薬を選択します。
小児気管支ぜんそくのQ&A
喘息発作が出現した時の応急処置はどうしたらいいですか
発作時の薬や吸入薬は、医師の指示に従って正しく使用しましょう。
使用時は上体を起こし、腹式呼吸を意識すると効果的です。
これらの薬を使用しても改善しない場合は、速やかに当院を受診してください。
発作時の対応について、事前に主治医に相談しておくことをお勧めします。
小児喘息で苦しい時はどうしたらいいですか?
お子さんの体を起こしてあげましょう。
体を起こすことで呼吸が楽になることがあります。
そして、ゆっくりと呼吸をするように促し、可能であれば腹式呼吸を意識させてみてください。
姿勢や呼吸法を試しても改善が見られない場合は、当院にご連絡ください。
喘息気味の時の対処方法はありますか?
喘息の症状がある時は、保育園、幼稚園、習い事などは控え、自宅で安静に過ごしましょう。
お子さんを預ける際は、症状悪化時の対応について、事前に預かる方と共有しておくと安心です。