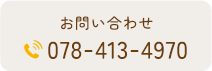子どもの便秘、続く便秘とは
 便秘は、子どもの約10%にみられる一般的な症状で、小児科では頻繫に見られる問題です。
便秘は、子どもの約10%にみられる一般的な症状で、小児科では頻繫に見られる問題です。
子どもの便秘かどうかを見極めるには、便の回数だけでなく、顔が赤くなる、排便時に出血する、お腹が張るといったサインに注意することが大切です。
便が出し切れない感じや、スッキリしない不快感も便秘の指標となります。
子どもの便秘は、風邪や体調不良が原因の場合もありますが、改善せず治療が必要な場合もあります。
便秘が慢性化すると、便が腸内に長く留まり、水分が失われて硬くなり、さらに便が硬くなる悪循環に陥ります。このような慢性便秘のお子さんには、薬物療法だけでなく、健康的な排便習慣を身につけるためのサポートが不可欠です。
当院では、エコー検査で、お子さんの腸内にどれだけ便がたまっているかを具体的に確認できます。
慢性便秘の場合、薬だけで様子を見るだけでは不十分で、「毎日スッキリと排便できて気持ちがいい」とお子さんが感じられるような、健康的な排便習慣を身につけるための適切なケアとサポートが必要です。
お子さんの状態をよく観察し、必要に応じて当院を受診していただき、最適なケアで健康的な成長をサポート致します。
便秘の基準や症状チェック
便秘とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?学会による定義を見てみましょう。
日本消化器病学会では、「排便回数の減少」を便秘と定義しています。
排便回数は個人差が大きく、1日2~3回の人もいれば、2~3日に1回の人もいます。
この範囲を外れる場合は異常の可能性がありますが、長年の習慣で苦痛がない場合は、必ずしも便秘とは限りません。
しかし、便秘薬を使わないと排便できない、または2日に1回でも腹痛や膨満感を伴う場合は、便秘として治療が必要でしょう。
一方、日本内科学会では、「3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態」を便秘と定義しています。
このように、学会によって定義が異なり、個人差も大きいのが現状です。
子どもの便秘についても、便が出ずに腹痛や膨満感、不快感などを感じている状態であれば、便秘と考えることができます。
症状チェック

- 数日間、排便がない事がありませんか?
- 便が硬くて、小さな塊状になっていますか?
- 排便時に、お子さんが苦痛や不快感を訴えていませんか?
- お腹の張りや腹痛を感じていませんか?
- 便の色や臭いにいつもと違う点はありませんか?
- 食欲低下が見られていませんか?
- いつもとは機嫌が異なったり、いつもより不機嫌になったりしていませんか?
- お腹を押したり、足を引っぱったりしていませんか?
これらの症状が見られる場合は、便秘の可能性があります。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
子どもの年代別 便秘の原因
便秘の原因は、年齢や食習慣など様々です。
乳児期
乳児の便秘は、多くが排便の力が弱いことが原因です。
母乳からミルクや離乳食に切り替える際、胃腸がまだ慣れていないため便秘になることもあります。
また、乳児用ミルクは母乳と比べて乳糖の作用が弱く、腸内ビフィズス菌が増えにくいことから、便秘になりやすい傾向があります。
幼児期
幼児期の便秘は、トイレトレーニングによって生じることもあります。
トイレでの排便に慣れていないと、排便を我慢してしまい、後から漏らしてしまうこともあります。
そして、親からの叱責によりストレスが溜まり、便秘になるケースもあります。
学童期
学童期の便秘の一つの原因は、「排便の我慢」です。
朝、学校へ行く時間がないためトイレタイムが十分に取れず、我慢してしまう子どもが多いのです。
学校では、授業時間や様々な理由でトイレに行くのが難しい場合もあります。
また、朝食を抜くことも便秘の原因となります。
朝食は腸の蠕動運動を促し、排便を促すため、朝食を食べないと、自然な排便リズムが乱れてしまいます。
子どもの便秘を放っておくと…
便秘が続くと、嘔吐や便失禁など、深刻な状態になる可能性があります。
嘔吐
 排出されない便が腸内に滞留することで、腸内環境が悪化し、胃腸への負担が増加し、結果、嘔吐につながることがあります。
排出されない便が腸内に滞留することで、腸内環境が悪化し、胃腸への負担が増加し、結果、嘔吐につながることがあります。
便失禁
便が直腸に溜まり続けると、便意を制御できなくなり、便が漏れてしまう便失禁が起こる可能性があります。
これはお子さんの心にも大きな負担をかける可能性があります。
便秘の治療
薬物療法
長時間、便が腸内に留まると徐々に硬くなり、排便時の痛みを伴うため、「排便=辛いもの」という認識につながる可能性があります。
当院では、お子さんが「排便=スッキリ気持ちいい」と感じられるよう、必要に応じて薬物療法を用います。
腸の働きを正常化する薬、便を柔らかくする薬、浣腸、漢方薬などを使用する場合があります。
生活習慣の見直し
規則正しい生活
 早朝に起床し、ゆっくりと朝食を摂ること、落ち着いて排便できる時間を作る、夕食を早めに済ませて早めに就寝するなど、規則正しい生活習慣を心がけましょう。
早朝に起床し、ゆっくりと朝食を摂ること、落ち着いて排便できる時間を作る、夕食を早めに済ませて早めに就寝するなど、規則正しい生活習慣を心がけましょう。
ただし、いきなり全てを変える必要はありません。
まずは、「起きたらまずトイレに行く」など、小さなことから始めてみましょう。
バランスの取れた食事
便秘改善には、特定の食品を大量に摂取するよりも、バランスの良い食事が大切です。
水分摂取も重要ですが、水分だけを多く摂っても便秘は改善しません。
食物繊維も効果的ですが、十分な量を継続して摂取するのは難しいです。
研究でも、便秘の子とそうでない子の食事内容に、食物繊維や水分摂取量に大きな差がないことが報告されています。
また、海外のガイドラインでも、通常の摂取量が推奨されています。
無理なく、栄養バランスの良い食事を心がける必要があります。
便意の我慢をしない
お子さんが便意を感じたら、すぐにトイレに連れて行きましょう。
便意を我慢すると、便秘が悪化する可能性があります。
また、トイレトレーニング中の場合は、焦らずゆっくりと進めることが大切です。
うんちの形のチェック
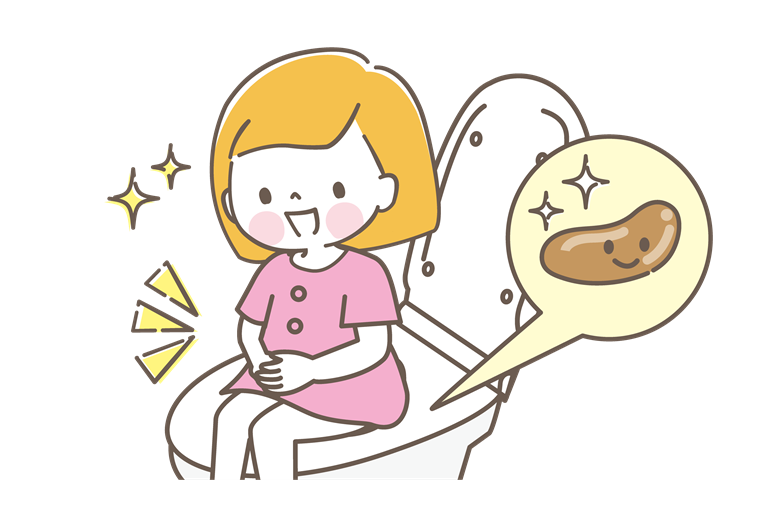 うんちは体調のバロメーターです。
うんちは体調のバロメーターです。
硬い便や下痢便は、大腸や肛門への負担が大きくなります。
便秘に伴う腹痛などの症状は、お子さんの心身にも悪影響を与えます。
理想的なうんちは、表面がツルツルしていて柔らかく、いきまなくても自然と出るバナナ状の便です。
この形を目指して、生活習慣を整えましょう。
お通じ日記
便秘が続く場合は、排便回数や便の状態を記録しましょう。
お子さんが楽しく記録できるよう、好きなキャラクターのノートやシール、スタンプなどを活用するのも効果的です。
お子さんと一緒に記録することで、排便に対してポジティブなイメージを持つようになり、治療がスムーズに進みます。
子どものうんちが出る・
便秘解消に役立つ食事とは?
子どもの便秘解消に有効な食生活の改善
 便は食べたもので作られます。
便は食べたもので作られます。
便秘改善には、食事内容を見直すことが効果的です。
ポイントは、「食物繊維をしっかり摂って腸内環境を整える」「オイル類を適度に摂って腸の動きを促進する」「腸内環境に良い働きをする菌を取り入れる」です。
積極的に取り入れたい
食べ物一覧
便秘のときに積極的に取り入れたい食べ物は以下のとおりです。
食物繊維を豊富に含む食品
食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。
水溶性食物繊維(昆布、わかめ、ひじき、こんにゃくなど)は便を柔らかくし、腸内移動をスムーズにします。
不溶性食物繊維(バナナ、ブルーベリー、きのこ、豆類、芋類など)は腸の動きを活発にし、便の量を増やします。
味噌汁に海藻を入れたり、おやつにバナナや干し芋を食べるなど、両方の食物繊維をバランスよく摂りましょう。
発酵食品
発酵食品である納豆、味噌、ヨーグルト、チーズ、キムチなどは、腸内環境を整える善玉菌を含んでいます。
お子さんが食べやすいものから、毎日の食卓に取り入れてみてください。
オイル類
ごま油、エゴマ油、オリーブオイル、ココナッツオイルなどは、腸を刺激して動きを活発にし、排便を促す働きがあります。
便の滑りを良くし、腸内移動をスムーズにする効果も期待できます。
炒め物だけでなく、パンに塗ったり、サラダやスープにかけたりして摂りましょう。
子どもの便秘のQ&A
便秘の原因は何?
便秘の原因は様々ですが、多くの場合は、明確な原因が特定できないケースがほとんどです。
食事習慣や精神的なストレスなどが影響していると考えられます。
まれに、生まれつきの腸の異常や他の病気が原因の場合もあります。
当院で推奨する治療法で改善しない場合は、より詳しい検査を行う場合があります。
心配なことがあれば、いつでもご相談ください。
便秘が起こりやすい時期ってある?
便秘になりやすいのは、生活環境が大きく変わる時期です。
母乳からミルクへの切り替え、離乳食開始、トイレトレーニングの開始、入園・入学など、生活リズムの変化は便秘の原因となります。
「水分をたくさん飲む」っていいの?
水分摂取は便秘予防に役立ちますが、水分だけで便秘が解消するわけではありません。
また、水分不足は便を硬くしますが、水分を摂るだけでは便が柔らかくなるわけではありません。
実際の便秘治療の基本は、便を柔らかくする薬(軟下剤)の服用です。
水分摂取は、薬の効果を高める補助的な役割を果たします。
「食物繊維」っていいの?
食物繊維は便の量を増やし、腸の動きを活発にする効果がありますが、十分な効果を得るには毎日一定量を摂り続ける必要があり、現実的には難しいです。
研究でも、便秘の子とそうでない子の食物繊維摂取量に大きな差がないことが報告されています。
食物繊維だけでなく、たんぱく質や脂質、ビタミン、ミネラルなど、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
「整腸剤」っていいですか?
整腸剤は腸内環境を整える働きがありますが、小児の慢性便秘に効果があるという明確な科学的根拠は少ないです。
そのため、全てのお子さんに効果があるわけではありません。
機能性便秘で基礎疾患がない場合、どうやって治療する?
生活習慣の見直しを基本とし、必要に応じて薬物療法を行います。
便を柔らかくする飲み薬、座薬、浣腸などを用います。
医師の指示に従って適切に使用しましょう。
長期間便秘が続く場合は、すぐに解消しようとせず、少しずつ改善を目指し、継続的なケアが大切です。