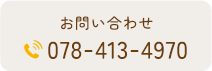早ければ1~2歳で花粉症!?
子どもの花粉症とは
 お子さんの花粉症は増加傾向にあり、5~9歳で13.7%、10~19歳では31.4%がスギ花粉症を発症しており、成人と同程度です。
お子さんの花粉症は増加傾向にあり、5~9歳で13.7%、10~19歳では31.4%がスギ花粉症を発症しており、成人と同程度です。
4歳以下でも数%がスギ花粉症で、花粉曝露の翌年から発症する可能性があるため、早ければ1~2歳で発症することもあります。
花粉症は花粉を吸い込むことで抗体が作られ、その量が増えることで発症します。
抗体の作られやすさには個人差がありますが、年齢を重ねるほど花粉曝露の機会が増えるため、発症リスクが高くなります。
そのため、低年齢での発症はまれで、小学校入学前後から増加します。
見逃しやすい
子どもの花粉症の症状
鼻詰まり
お子さんの花粉症でよくみられるのは鼻づまりです。
夜間に何度も目が覚めたり、口呼吸になる場合があるので注意が必要です。
粘りのある鼻水
大人のサラサラした鼻水とは異なり、お子さんの花粉症では粘り気のある鼻水が出ることがあります。
これも鼻づまりの影響と考えられます。。
目のかゆみ、充血
目のかゆみによって、目の周りをこすったり押さえたりする仕草が見られます。
目の充血やむくみもよくみられる症状です。
早期発見のポイント
鼻をよく啜る
鼻をかむのが苦手なため、大人より鼻をすする回数が増える傾向があります。
鼻や口をもごもごさせる
中耳炎や副鼻腔炎の発症や悪化につながる可能性があります。
自然治癒しない
食物アレルギーと違い、成長とともに自然治癒することはありません。
子どもの花粉症は何科で
受けられる?検査・診断
大人の花粉症は、症状に応じて内科、耳鼻科、眼科を受診しますが、お子さんの場合は、継続的に診てもらえる小児科が最適です。
当院では、専門的な対応・治療を提供していますので、安心してご相談ください。
血液検査
アレルギーの原因物質を特定するための検査です。
指先からの採血も可能なので、注射が苦手な小さなお子さんでも検査を受けることができます。
皮膚テスト
アレルギーの原因物質を特定するための検査で、皮膚に抗原を作用させ、反応を調べます。
痛みやかぶれはほとんどありません。
スクラッチテスト(皮膚に軽い傷をつけ抗原を滴下)やプリックテスト(抗原を滴下後、針で軽く押す)などの方法があります。
鼻鏡検査
鼻の中に光を当て、粘膜の状態を観察する検査です。
鼻の穴を広げ、粘膜の腫れや鼻水の状態を確認します。
アレルギーの原因特定はできませんが、花粉症か他の疾患かの鑑別に有用です。
子どもの花粉症の治療
花粉症は、食物アレルギーとは異なり、成長とともに自然治癒することは稀です。
症状悪化を防ぐため、服薬、マスク着用、吸引・吸入などの対策を行いましょう。
スギ花粉症の場合は、根治を目指す免疫療法を強くお勧めします。
吸引・吸入
鼻の粘膜の状態を良好に保つためには、マスク着用による花粉対策や、こまめな吸引・吸入も重要です。
内服薬
抗アレルギー薬には、赤ちゃんにも服用しやすいシロップ、ドライシロップ、チュアブルタイプがあります。
初期治療が重要ですので、抗アレルギー薬を適切に使用し、症状の悪化を防ぎましょう。
舌下免疫療法
舌下免疫療法は、ダニやスギなどのアレルギー物質の錠剤を舌の下に含む治療法です。
自宅で1日1回服用するだけなので、痛みや負担が少ない治療です。
他の薬物療法とは異なり体質改善を目的とするため、根本的な治療と言えます。
皮下免疫療法
アレルゲン免疫療法には、舌下免疫療法と皮下免疫療法があります。
舌下免疫療法は比較的新しい治療法ですが、皮下免疫療法は以前から行われている治療法です。
皮下免疫療法は、アレルゲンを含む薬剤を注射で投与し、アレルギー反応が起こりにくい体質を目指します。
増量期は週1回程度の通院が必要ですが、維持期は月1回で済むという利点があります。
効果は舌下免疫療法と同等で、こちらを選択される患者さんもいらっしゃいます。
詳細は当院スタッフまでお問い合わせください。
子どもの花粉症対策・
予防ポイント
花粉症予防の最善策は、花粉との接触を避けることです。
雨上がりや晴天時、強風時は花粉飛散量が増加するため、状況に合わせた対策が必要です。
具体的には、以下の点にご注意ください。
- 花粉飛散期はマスクを着用する。
- 長時間屋外で遊ばない。
- 換気を最小限にする。
- 洗濯物はなるべく室内に干す。
- こまめに掃除機をかける。