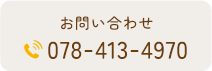子どもの背の伸びが気になる…
もしかして「低身長」?
 お子さんの身長は、主に遺伝や体質の影響を受けますが、成長ホルモンの不足や、低出生体重児でその後あまり身長が伸びない場合など、低身長のケースもあります。
お子さんの身長は、主に遺伝や体質の影響を受けますが、成長ホルモンの不足や、低出生体重児でその後あまり身長が伸びない場合など、低身長のケースもあります。
まれに、染色体異常や骨の病気などが原因となることもあります。
子どもの低身長の基準や
受診の目安
成長速度が5cm/年
通常、お子さんは1年で5cm以上成長します。
それ以下が続く場合、低身長(身長標準偏差値(身長SDS)が-2SD以下)の可能性があります。
身長標準偏差値スコア
(身長SDS)が
「-2SD」以下
医学的には、身長SDSが-2SD以下を低身長と定義します。
同じ性別・年齢の子ども100人を背の順に並べたとき、前から2~3番目の子どもが該当します。
成長曲線が気になる
成長曲線で、3歳頃から身長の伸びが停滞している場合、成長ホルモン分泌不全の可能性があります。
また、成長が止まるケースや、思春期早発症で急激に身長が伸びるケースでは、成長曲線の変化を見逃さないことが大切です。
受診の目安について
身長SDSが-2SD以下、または1年間の成長速度が5cm未満の場合、もしくは成長曲線に気になる点があれば、受診をおすすめします。
低身長症の検査・診断
問診
これまでの成長記録や日常生活についてお伺いします。
母子手帳をお持ちいただくと、成長曲線作成の際に役立ちます。
計測
身長と体重を測定し、-2SD以下かどうかを確認します。
診察
基本的な診察とともに、全身のバランス、甲状腺の状態、外表奇形の有無などを確認します。
一次検査
(スクリーニング検査)
血液検査
- 貧血、生化学検査
- ソマトメジンC
- 甲状腺機能検査
レントゲン検査
- 手の骨による骨年齢の検査
染色体検査
女児の場合、ターナー症候群の疑いがあれば染色体検査を行う場合があります。
二次検査
(成長ホルモン分泌検査)
一次検査で成長ホルモン分泌不全の疑いがある場合、成長ホルモン分泌試験を行います。
病気が原因?それとも個性?
低身長症の2つのタイプ
①病気ではない
個性としての低身長症
低身長の子どもの多くは、検査で異常が見つからないケースです。
これは病気ではなく、個性の一つと考えられます。
家族性低身長、体質性低身長、二次性徴がゆっくり進む思春期遅発などが挙げられます。
家族性低身長
検査で異常がなく、両親または片親が低身長の場合、家族性低身長の可能性があります。
身長は遺伝的要素が大きく、両親の身長と相関関係があります。
予測身長の計算式もありますが、必ずしも正確ではありません。
家族全員の体格が小さく、他の病気の疑いがない場合は、家族性低身長の可能性が高いです。
しかし、極端な低身長の場合は、他の病気を疑い、検査を行うこともあります。
身長を伸ばす要素
身長は遺伝だけでなく、様々な要素が影響します。
骨の成長を促すには、規則正しい生活習慣、適度な運動、質の良い睡眠、適切な栄養摂取が重要です。
睡眠
成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。
特に、眠り始めの深い睡眠時に最も分泌が盛んとされています。
朝日を浴び、日中は活動的に過ごし、夜は部屋を暗くして、質の高い睡眠をとれるようにサポートしましょう。
また、ブルーライトを避けるため、寝る前のスマホやタブレットの使用は控えましょう。
栄養素
成長期における身長を伸ばすためには、食事はとても重要です。
特に以下の栄養素は不可欠です。
カルシウム
骨の主成分であり、成長期には十分な摂取が必要です。
牛乳、ヨーグルト、豆腐、チーズ、干しエビ、ごま、ひじき、きな粉などに多く含まれています。
ビタミン
ビタミンDは日光浴でも生成されます。
魚介類、卵、きのこ類に多く含まれ、カルシウムの吸収を助けます。
ビタミンKは骨を丈夫にする働きがあり、納豆、モロヘイヤ、小松菜、ブロッコリー、わかめなどに多く含まれています。
アルギニン・シトルリン
これらのアミノ酸は、成長ホルモンの分泌を促します。
うなぎやにんにくなどに多く含まれています。
運動
適度な運動は成長ホルモンの分泌を促し、食欲増進、睡眠の質向上にもつながります。
大切なのは、お子さんが楽しく運動を続けることです。
激しい運動は、体ができてから行う方が良いでしょう。
②病気によって
引き起こされる低身長症
低身長の原因は、遺伝や体質によるものが大半ですが、成長ホルモンなどの分泌不足、染色体異常、骨の病気、低出生体重児でその後の成長が不十分な場合など、病気が原因となることもあります。
これらの病気は稀ですが、治療可能なものもあり、適切な治療で改善できる可能性があります。
| ホルモンの異常によるもの |
| 成長ホルモン、甲状腺ホルモンの分泌不足など |
| 染色体の異常によるもの |
| ターナー症候群、プラダー・ウィリー症候群、ヌーナン症候群など |
| 小さく生まれたことに関係するもの |
| SGA(Small-for-Gestational Age)性低身長症など |
| 骨や軟骨の異常によるもの |
| 軟骨異栄養症(軟骨無形成症、軟骨低形成症)など |
| 心臓・肝臓・腎臓など主要臓器の 異常によるもの |
| 小児慢性腎不全など |
| 環境によるもの(心理社会的原因) |
| 愛情遮断症候群 |
低身長症の治療
ホルモン異常
脳下垂体の障害などで成長ホルモンが不足すると、身長の伸びが悪くなります。
甲状腺機能低下症も低身長の原因となります。
これらのホルモン不足には、ホルモン補充療法で改善が期待できます。
ターナー症候群
女児に約2000人に1人の割合でみられる染色体異常です。
低身長のほか、卵巣機能低下による思春期発来の遅れ、心臓病や難聴などの合併症を伴う場合があります。
成長ホルモン療法や女性ホルモン療法を行います。
プラダー・ウィリー
症候群、ヌーナン症候群
プラダー・ウィリー症候群は15番染色体の変化による病気で、低身長、性腺発育不全、肥満、発達障害などの症状があります。
ヌーナン症候群は遺伝子変異が原因で、特徴的な外見、低身長、思春期遅発、心疾患などを特徴とします。
いずれも、低身長に対しては成長ホルモン療法を行います。
SGA(Small-for-Gestational Age)
性低身長症
在胎週数に対して小さく生まれた場合、低身長が続くことがあります。
多くの場合3歳までに追いつきますが、追いつかない場合はSGA性低身長症と診断されます。
特定の条件を満たせば、成長ホルモン療法による治療が行われる可能性があります。
軟骨異栄養症
(軟骨無形成症、
軟骨低形成症)
遺伝子の異常により骨や軟骨の成長に影響が出る病気です。
骨の成長が不均一で、手足が短くなるなどの症状が現れます。
成長ホルモン療法や骨延長術を行います。
主要臓器の異常
心臓、消化器、肝臓、腎臓などの疾患は、栄養吸収を阻害し、低身長につながることがあります。
それぞれの疾患に対する治療を行うことで、身長の伸びも改善される可能性があります。
低身長の検査で、隠れていた臓器の病気が見つかることもあります。
愛情遮断症候群
心理的ストレスが成長を阻害する愛情遮断症候群では、適切な愛情、栄養、養育環境の提供が重要です。
育児ノイローゼなどが影響している可能性もあり、周囲の支援が重要となる場合もあります。