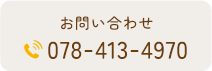子どもの溶連菌に
気づかず放置…
溶連菌感染症とは
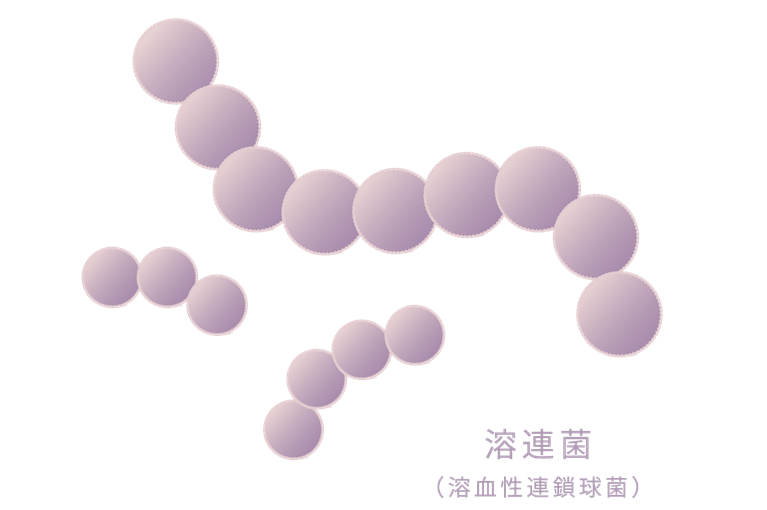 溶連菌感染症は、A群β溶血性連鎖球菌への感染によって起こります。
溶連菌感染症は、A群β溶血性連鎖球菌への感染によって起こります。
主に、菌を含む飛沫の吸入や、汚染された食品の摂取により感染します。
5歳頃をピークに4~10歳の子どもに多く、幼稚園や小学校などで流行しやすい傾向があります。
大人も感染する可能性はあります。
当院では、感染経路や流行状況を踏まえた対策を講じています。
溶連菌になりやすい
時期は?
溶連菌感染症は、溶連菌が咽頭や皮膚に感染する病気です。
咽頭感染は12~3月、皮膚感染は7~9月に多く発生する傾向があります。
溶連菌は喉を見たらわかる!?症状チェック・潜伏期間
溶連菌の症状
全身の発疹
発症1~2日目に、顔や体(特に脇の下、下腹部)に、かゆみのある小さくて赤い発疹が多数現れます。
咽頭炎・扁桃腺炎
強い咽頭痛と扁桃腺の腫れに加え、扁桃腺に白いものが付着しているのが観察されます。
唾を飲み込むと激痛が走るほどの、強い咽頭痛を伴います。
舌にイチゴのようなボツボツができる
発症2~4日目には、舌の表面がイチゴのように変化します。
口蓋にボツボツした出血斑ができる
口の中に、小さな点状の出血斑が出現します。
当院では、口腔内の変化も確認しながら診断を進めます。
皮が剥ける
他の症状が治まった後、5~6日目以降に手足の指先から皮膚の剥離が始まります。
当院では、回復期における皮膚の変化についても説明しています。
溶連菌の潜伏期間は
どのくらい?
溶連菌感染症の潜伏期間は2~5日程度で、無症状のため感染に気づきにくいのが特徴です。
当院では、感染拡大防止のため、早期発見・早期治療に努めています。
受診の目安は?
 溶連菌感染症は自然治癒することもありますが、合併症予防と症状緩和のため、早期の受診をお勧めします。
溶連菌感染症は自然治癒することもありますが、合併症予防と症状緩和のため、早期の受診をお勧めします。
特に、以下の症状がある場合は、脱水症状や合併症の可能性があるため、必ず当院を受診してください。
- 呼びかけに反応せず、視線が合わない
- 呼吸が速く息苦しそうにしている
- けいれんを起こした
- 嘔吐を繰り返している
- 高熱が4日以上続いている
- 泣いても涙が出ず、尿少ない
- 口の中や唇が渇いている
- 元気がなくぐったりしている
- 喉の痛みが強く、唾液や水分が飲み込めない
溶連菌の検査・診断
溶連菌感染症は抗体産生により自然治癒も期待できますが、合併症予防のため、早期の検査・診断・治療をお勧めします。
迅速検査
咽頭ぬぐい液を採取し、約15分で判定できる迅速検査で診断します。
ただし、抗生物質服用後は正確な判定が難しい場合がありますので、ご来院の際はお申し出ください。
培養検査
迅速検査とは異なり、咽頭ぬぐい液を培養して判定するため、結果が出るまで数日かかります。
少量の菌でも検出可能ですが、抗生物質服用後は正確な判定が難しい場合があります。
受診の際はお申し出ください。
抗体検査
血液中の抗体価を測定する検査で、外部機関に委託するため、結果が出るまで時間を要します。
ご不明な点は、当院までお問い合わせください。
溶連菌の治療法や予防法
 溶連菌感染症の治療は抗菌薬の内服です。
溶連菌感染症の治療は抗菌薬の内服です。
服用により、1~2日で解熱し、発疹も軽快、咽頭痛も1週間以内に治まります。
その後、指先の皮膚が剥離しますが、約3週間で治まります。
3歳未満のお子さんの場合、発熱や発疹が出ず、咽頭炎のような症状で経過することもあります。
ただし、検査で溶連菌感染症と診断された場合は、適切な治療が必要です。
抗菌薬が有効ですが、処方された量と回数を厳守することが重要です。
症状が改善しても、自己判断で服薬を中止せず、処方された期間きちんと服用してください。
まれに、急性糸球体腎炎、リウマチ熱、アレルギー性紫斑病などの合併症が起こる場合があります。
リウマチ熱予防のため、医師の指示に従い、抗菌薬を10日程度服用する必要があります。
治癒後3~4週間に急性糸球体腎炎発症の可能性があり、尿検査を行って参ります。
子どもの溶連菌感染時に
家庭で気を付けたいこと
溶連菌感染症は感染力が強いため、咳やくしゃみの飛沫などを介して感染します。
感染予防のため、以下の対策を心がけましょう。
- お子さんが触れるものを清潔に保つ
- 食器やタオルは共有しない
- こまめな手洗いとうがい
- 看病時はマスクを着用する