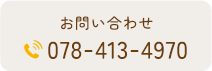予防接種について
 赤ちゃんは母親から免疫を受け継ぎますが、生後数ヶ月でその効果はなくなります。
赤ちゃんは母親から免疫を受け継ぎますが、生後数ヶ月でその効果はなくなります。
その後は、感染症にかかることで免疫を獲得していく必要がありますが、予防接種によって感染せずに免疫を得ることが可能になります。
お子さんの成長とともに、外出や集団生活の機会が増え、感染症のリスクも高まります。
予防接種は、感染症の予防、そして発症した場合の重症化を防ぐために重要です。当院では、保護者の方もご一緒に、インフルエンザワクチンなど接種可能です。お気軽にお問合せください。
子ども・赤ちゃんの予防接種のときの持ち物や服装は?
予防接種時には、初回も2回目以降も、基本的に以下のものをご持参ください。
予防接種を受けるのに
必要なもの
- 母子手帳
- 健康保険証
- 診察券(お持ちの方)
- 予診票、接種券
- 乳幼児医療証
- 現金(任意接種の場合)
赤ちゃんのお世話に
役立つ必要なもの
- ミルクや飲み物
- 抱っこひも(ベビーカーの場合も持参すると安心です)
- お気に入りのおもちゃ(あれば)
- おむつ
- 着替え
予防接種当日の服装の
ポイント
予防接種当日は医師の診察がありますので、脱ぎ着しやすい服装でお越しください。
前開きの服、股にスナップボタンが付いている服、上下セパレートの服などがおすすめです。
ワンピースやサロペットなどは避けましょう。
寒い時期は、カーディガン、ベスト、ブランケットなどを活用し、体温調節してください。
ニットやトレーナーは脱ぎ着しにくいので避けた方が良いでしょう。
予防接種の当日接種できない場合
- 体温が37.5℃以上の場合
- 医師が接種不適当と判断した場合
- (定期接種の場合)予診票・接種票の確認ができない場合
ワクチンの種類
生ワクチン
生ワクチンは、弱毒化した病原体を使用し、体内で自然増殖することで高い抗体産生を促します。
接種回数が少なくても効果が高いのが特徴です。
国内で使用されている生ワクチンには、MR混合(麻疹、風疹)、水痘、おたふく風邪、ロタウイルス、BCG(結核)などがあります。
不活性化ワクチン
不活化ワクチンは、病原体の毒性を完全に無効化し、抗原となる成分のみを残したワクチンです。
生ワクチンに比べ抗体産生力は弱いため、複数回の接種が必要となる場合があります。
このタイプのワクチンには、B型肝炎、ポリオ、肺炎球菌、百日咳、日本脳炎、インフルエンザ、ヒブ(ヘモフィルス・インフルエンザ菌b型)などが含まれます。
トキソイド
トキソイドは、病原体の毒素を無毒化し、抗体産生能のみを残したワクチンです。
生ワクチンと比較して抗体産生力は弱いため、複数回の接種が必要となる場合があります。
日本では、ジフテリア、破傷風に対するトキソイドが使用されています。
予防接種の一覧(定期・任意)
定期予防接種
ロタ(ロタテック)
予防する病気
ロタウイルス感染症(嘔吐や下痢を引き起こすロタウイルス胃腸炎、脳炎などの重篤な合併症を含む)を予防します。
接種年齢・回数
ロタウイルスワクチンの接種は生後6週から可能ですが、他のワクチンとの同時接種を考慮し、生後2ヶ月からの接種が最適です。
ワクチンの種類により接種回数は2回または3回です。
初回接種は14週6日までに完了することが推奨されており、接種期間が限定されています。
これは他のワクチンとは異なる点です。
早期に接種することで、腸重積症*(腸閉塞の一種)のリスクを低減することを目的としています。
四種混合(DPT-IPV)
予防する病気
ジフテリア(D)、百日咳(P)、破傷風(T)、ポリオは、特に乳児期に重症化のリスクが高い感染症です。
百日咳は、脳炎や重症肺炎などの合併症を引き起こし、生命に関わる危険性があります。
接種年齢・回数
接種開始は生後3ヶ月から可能です。
3~8週間隔で3回接種し、追加接種を1年後に行います。
計4回の接種を7歳6ヶ月までに完了します。
二種混合(DT)
予防する病気
ジフテリア(D)、破傷風(T)を予防します。
接種年齢・回数
11歳から12歳頃に1回接種します。
BCG
予防する病気
BCGは、結核を予防します。
接種年齢・回数
BCG接種は、生後6ヶ月までは定期接種、それ以降は任意接種となります。
専用の針で2回、スタンプのように圧迫して接種します。
MR(麻疹風疹混合)
予防する病気
麻疹(はしか)、風疹を予防します。
接種年齢・回数
麻疹風疹混合(MR)ワクチンは、1歳と小学校入学前年の2回接種します。
1回目の接種は、1歳の誕生日を迎えてすぐに行いましょう。
日本脳炎
予防する病気
日本脳炎の発症率は低いものの、ウイルスは関東近郊の養豚場などで高い陽性率を示しており、突発的な流行の危険性があります。
接種年齢・回数
日本脳炎ワクチンは、2期に分けて接種します。
1期:生後6ヶ月から7歳半未満までに、1~4週間隔で2回接種します。
追加接種は、2回目接種から約1年後(標準年齢は4歳)に1回接種します。
2期:9歳から12歳(標準年齢は9歳)に1回接種します。
ヒブ(Hib)
予防する病気
ヒブ感染症(細菌性髄膜炎、喉頭蓋炎、肺炎、敗血症などの重篤な感染症)を予防します。
接種年齢・回数
ヒブワクチンは年齢によって接種回数が異なります。
生後2ヶ月~6ヶ月未満:4回
生後7ヶ月~1歳未満:3回
1歳~4歳:1回
5歳以上:接種不要
初回接種は生後2ヶ月から3ヶ月頃までに受けることが推奨されます。
小児用肺炎球菌(プレベナー)
予防する病気
小児の肺炎球菌感染症(細菌性髄膜炎・菌血症、菌血症を伴う肺炎など)を予防します。
接種年齢・回数
肺炎球菌ワクチンは年齢によって接種回数が異なります。
生後2ヶ月~6ヶ月未満:4回
生後7ヶ月~1歳未満:3回
1歳:2回
2歳~9歳:1回
初回接種は、生後2ヶ月から3ヶ月頃までに受けることが推奨されます。
水痘(みずぼうそう)
予防する病気
水痘(みずぼうそう)を予防します。
接種年齢・回数
水痘ワクチンは1歳から接種可能です。
十分な免疫獲得のため、1回目接種から3ヶ月~1年後に2回目の接種が必要です。
B型肝炎
予防する病気
B型肝炎を予防します。
接種年齢・回数
B型肝炎ワクチンは生後2ヶ月から接種可能ですが、生後1ヶ月~3ヶ月頃からの接種が推奨されます。
接種スケジュールは、4週間の間隔を空けて2回接種した後、20~24週間後に3回目の接種を行います。
大人を含め、どの年齢からでも接種可能です。
五種混合
予防する病気
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ(Hib)感染症を予防します。
接種年齢・回数
五種混合ワクチンは、生後2ヶ月から90ヶ月までの間に接種します。
1回目から3回目までは20日以上(約20~56日)の間隔をあけ、3回目から4回目までは6ヶ月以上(約12~18ヶ月)の間隔をあけて接種してください。
任意予防接種
おたふくかぜ
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は、主にお子さんに発症するウイルス感染症です。
感染後2~3週間で耳下腺の腫れや発熱などの症状が現れます。
難聴、脳炎、精巣炎、無菌性髄膜炎などの合併症を引き起こすこともあり、特に難聴は完治が困難です。
そのため、おたふくかぜの予防は重要であり、1歳頃と小学校入学前の2回のワクチン接種が推奨されています。
インフルエンザ
インフルエンザワクチンは、発症予防だけでなく、感染した場合の症状緩和、肺炎や脳症などの合併症予防にも効果が期待できます。
ワクチンの効果は約2週間後に出現し、約5ヶ月間持続します。
13歳未満のお子さんは2回接種が推奨されます。
インフルエンザウイルスは毎年変化するため、ワクチンも毎年更新されます。
お子さんの健康を守るため、流行前に毎年接種することが大切です。